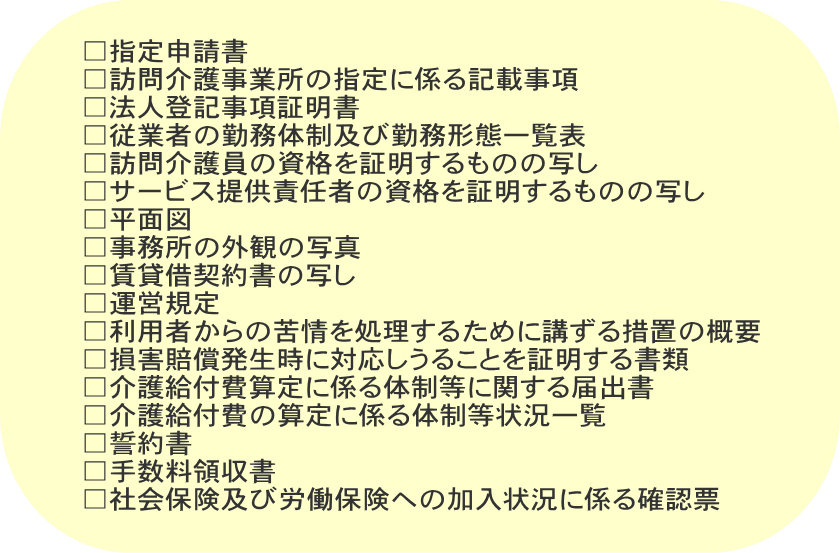遺言・相続
- 公正証書遺言
- 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証役場で、口頭で述べ、それに基づいて、公証人が文章にまとめて作成するものです。
自筆証書遺言か公正証書遺言かの選択については、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。公正証書遺言 自筆証書遺言 メリット 公証人が作成するので無効になる確率が少ない
原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造がない
再発行ができる
検認手続きが不要自分で簡単に作成できる
費用を低く抑えることができる
誰にも内容を知られずに作成することができる
証人がいらないデメリット 費用と手間がかかる
証人2人必要自分で作成するので無効となる可能性が高い
意思能力等の問題により無効の場合がある
遺言書を紛失する可能性がある
第三者に偽造される恐れがある
法務局の保管制度を利用しない場合、検認が必要
- 公正証書遺言作成の流れ
-
- STEP1
- お申し込み後、事前のご相談、打ち合わせ
- STEP2
- 相続人調査及び財産調査
- STEP3
- 遺言書の原案作成
- STEP4
- 公証人との打ち合わせ(当事務所で公証人と打ち合わせをします)
- STEP5
- 遺言書の内容を確認(内容の最終確認を行います)
- STEP6
- 遺言書が完成(公証役場に出向き、公証人が読み上げる遺言の内容を確認し、署名・押印)
- お手軽、公正証書遺言作成サービス
- 33,000円(税込)
 当事務所では、報酬額は必要書類の収集等に費やす労力と時間により決定いたします。
当事務所では、報酬額は必要書類の収集等に費やす労力と時間により決定いたします。
公正証書遺言作成=○○○○○円といった一律の設定はしておりません。
詳細はコチラ>>> - 財産調査の仕方
- 財産調査の対象となる財産の例
- 預貯金 有価証券 不動産 不動産上の権利 動産(自動車 宝飾品 貴金属 美術品等) 現金等
不動産の調査方法
市区町村から毎年届く、固定資産税の納税通知書を確認します。
納税通知書には、土地や家屋の地番や所在が記載されています。
納税通知書が見つからない場合には、市区町村に出向き、名寄帳や固定資産税の評価証明書を発行してもらいましょう。
なお、税金がかからない不動産については、納税通知書に記載されていない場合がありますのでご注意ください。
また、不動産が共有の場合もあります。不動産の登記を取得して内容を確認しましょう。
自宅内の通帳を確認します。金融機関に残高証明書及び取引履歴を請求します。
預貯金の調査方法
なお、通帳やカードが見つからない場合は、郵便物、名刺、粗品等を手掛かりに金融機関を特定します。
ネット銀行を利用していた場合は、メールの履歴、閲覧記録やブックマーク等を手掛かりに探します。
以上のような手掛かりがない場合は、被相続人の居住していた地域の金融機関を徹底的に調べていきます。
口座や店舗名が分からない場合は、全店照会を利用して、その金融機関のすべての店舗の口座を調べてもらいます。 - 預貯金 有価証券 不動産 不動産上の権利 動産(自動車 宝飾品 貴金属 美術品等) 現金等
相続手続き
- 相続手続きサポート
- 当事務所における相続手続きサポートは以下のとおりです。
- 遺言書の作成
相続人の調査
財産目録の作成
遺産分割協議書の作成
預金口座の相続手続き
自動車名義変更手続き
有価証券の相続手続き
- 遺言書の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 公証人手数料
- 公証人手数料はコチラ>>>